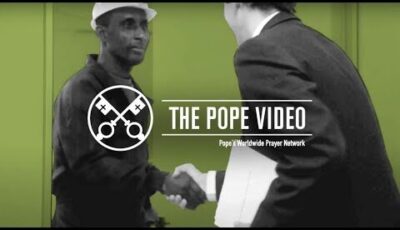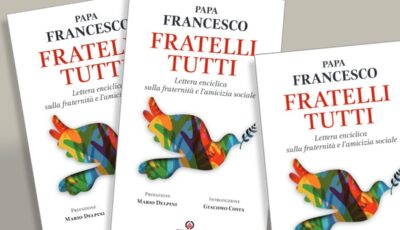STWRは、世界資源の分かち合いを最も声高に、そして謙虚に提唱したフランシスコ教皇の逝去を受け、哀悼の意を表します。
2013年に聖ペテロの位に就いて以来、教皇は、農業生態学から脱成長経済、化石燃料の投資撤退、武器取引規制、そして世界的な通貨改革に至るまで、進歩的な活動家にとって大切な多くの大義を擁護してきました。
しかし、彼の主張の中心にあったのは、世界的にも国家レベルでも不平等を終わらせることに焦点を当て、政府に対し、新たな寛大さの精神をもって富と利益を貧困層に再分配するよう繰り返し呼びかけてきたことでした。
STWRでは、2014年にフランシスコ教皇が国連に対し、今日世界中で蔓延している「排除の経済」を抑制するために、貧困層との連帯による「世界的な倫理的動員」を促進するよう促した、注目を集めた演説に衝撃を受けたことが思い出されます。
1年後の2015年、教皇は回勅『ラウダート・シ』(副題は「共通の家を大切にすることについて」)を発表し、自由放任主義の思想とその環境破壊的な影響を力強く批判し、世界中で大きな注目を集めました。この痛烈な書簡は、先進国が途上国に対する「環境負債」に対処する責任を説き、気候変動対策における「差異ある責任」を認めました。これは、南北間の資源移転と、先進国における再生不可能なエネルギー消費の大幅な削減を強く訴えるものでした。
『ラウダート・シ』の雄弁な言説は、多くの環境活動家が抱く核心的な認識、すなわち気候危機と不平等の危機は密接に関連しているという考えを反映しています。フランシスコ教皇は、広く蔓延する人々の苦しみに対する私たちの集団的な無関心を、繰り返し非難しました。彼は、国家の福祉は相互に関連しており、発展途上国の脆弱な経済が経験する深刻な貧困と飢餓は、ひいては自然環境の破壊に反映されていると、粘り強く主張しました。だからこそ、世界中の生活水準の大きな格差を是正することが急務であり、人類社会において悲劇的に欠如している、世界的な連帯感と相互依存の意識が不可欠なのです。
新型コロナウイルスのパンデミックの間、フランシスコ教皇は、富裕国が協力し、自国を優先して資源を蓄えるのではなく、ワクチンを世界に無償で配布するという課題も提示しました。2020年の回勅「Fratelli tutti(皆兄弟)」は、新型コロナウイルス感染症が既存の不平等を露呈させていること、そして人権平等に意味を与えるためには、国家レベルの友愛において富裕国が貧困国を支援する必要があることを明確にしました。貧困、不平等、そして気候変動という緊急事態への対策として「公正かつ尊重される方法で資源を分かち合う」というフランシスコ教皇の訴えを、世界は明らかに聞き入れませんでした。
フランシスコ教皇が繰り返し訴えたもう一つのテーマは、返済不能国の債務免除の必要性でした。2025年の聖年に向けた最後の教皇勅書「希望は欺かない」の中で、フランシスコ教皇は債務免除を寛大さよりも正義の問題と表現し、南北間の真の環境負債を改めて非難しました。
フランシスコ教皇は、最も脆弱で周縁化された人々の味方として、まさに「周縁化された人々の教皇」として知られていました。西側諸国の政府による先制的な政策や国際移民への過酷な対応に反対する姿勢を明確に示していました。就任直後、彼はイタリアのランペドゥーサ島を訪れ、小型ボートで地中海を渡る移民の溺死に対する欧州の「無関心」を非難しました。その後、「宙ぶらりんの幽霊のような生活」を送る、疎外された移民や難民のキャンプを数多く訪問し、見知らぬ人やアウトサイダーの中にキリストを見出すよう呼びかけました。これはトランプ、メローニ、オルバンといった反動的な政治家たちへの痛烈な非難であり、教皇が名を冠したアッシジの聖フランチェスコに影響を受けた「普遍的な友愛」の必要性を強調するものでした。
ガザでの停戦を呼びかけた数時間後に亡くなったことは、貧しい人々や忘れられた人々を擁護するフランシスコ教皇の姿勢を的確に証明するものでした。亡くなる前日のイースターの日曜日に送った恒例の「ウルビ・エト・オルビ (都市と世界へ)」メッセージで、戦闘当事者に対し、「平和な未来を切望する飢えた人々に援助の手を差し伸べてください」と繰り返し訴えました。12年間に及ぶ教皇在位中、彼の助言に従った政治家はほとんどいないようです。今や、善意を持つ私たち一般市民が、フランシスコ教皇のたゆまぬ擁護活動とより良い世界の希望を支える番です。
Image credit: Pope Francis in St Peter’s square by Alfredo Borba, Wikimedia commons