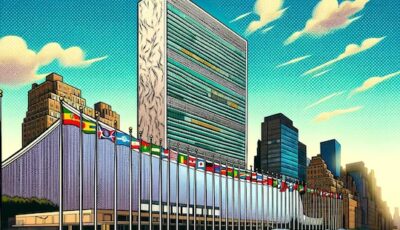どうすれば人類の幸福を促進しながら、地球を守れるのでしょうか?その両方を実現するには、格差を劇的に減らす以外に選択肢はない、とLSEにケイト・ピケット氏は書いています。
2009年に『スピリット・レベル』を出版した際、不平等の蔓延する影響を明らかにし、精神疾患から投獄率の上昇、社会流動性の低さ、乳児死亡率の高さに至るまで、幅広い健康問題や社会問題と関連付けることで、研究結果が再分配政策と平等重視の政治の新たな時代への警鐘となることを期待していました。しかし、現実は緊縮財政、ブレグジット、戦争と紛争、世界的なパンデミック、そして生活費の高騰といった状況でした。全く進展はありませんでした。
しかしながら、ここ15年ほどで不平等の問題への認識は多少前進しました。世界は超富裕層を許容できないことがますます明らかになっています。
事態は激化している
最も裕福な1%は、世界人口の最も貧しい半分の平均的な人の100倍の温室効果ガスを排出しています。気候危機に立ち向かうには、彼らの膨大な環境フットプリントの削減が不可欠であると認識される必要があります。しかしそれに加え、富裕層の消費は、模倣やステータス商品の消費増加につながることが示されています。研究によると、ステータス商品の消費は格差の大きい国ほど高いことが示されています。ステータス向上への不安や、広告主が私たちのステータスと自己顕示への関心を際限なく利用しているのです。
所得、富、政治力の不平等は、私たちが直面している複数の環境危機の根底にあります。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、「我々は皆、同じ海に浮かんでいるが、中にはスーパーヨットに乗っている人もいれば、漂流するゴミにしがみついている人もいるのは明らかだ」と述べ、「我々は皆、同じ海に浮かんでいる」という神話を打ち砕きました。
約80億の人々と50億の生物が地球の資源を共有している今、地球の限界にとどまりながら、盲目的に経済成長を追求することはできません。そのため、15年を経て「スピリット・レベル」の分析を更新するにあたり、当初焦点を当てていた健康問題や社会問題に加え、環境問題にも目を向けることにしました。
図1:環境問題は所得格差と強く関連している

私たちの新しい環境問題指数は、格差の大きい富裕国ほど環境問題への取り組みが劣っていることを示しています(図1)。この指数には、大気汚染、廃棄物のリサイクル、富裕国の二酸化炭素排出量、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成状況、国際協力(国連条約の批准と一方的な強制措置の回避)という5つの変数が含まれています。
地球の健全性には、格差の少ない社会が不可欠
私たちは、環境問題への取り組みにはさらに多くのことを行う必要があることを認識しており、気候変動と環境悪化がすべての人に平等に影響を与えるわけではないことも認識しています。脆弱な立場にある人々、そして低所得国・中所得国がその矢面に立たされており、公正な移行の必要性を浮き彫りにしています。人々が変化に伴う避けられない負担と、それを推進するために必要な政策が公平に分担されていると感じない限り、持続可能性に向けた動きは広範な反対に直面することになるでしょう。
所得格差の拡大は、政治的・社会的結束を弱め、環境問題への取り組みを支援する意欲を低下させます。対照的に、平等性の向上は、より協力的で相互扶助的な国民の形成につながります。例えば、統合世界価値観調査(Integrated World Values Survey)と欧州価値観調査(European Values Survey)のデータを用いた最近の分析では、より平等な国では、国民が経済成長よりも環境保護を重視する傾向があることが分かりました。格差の少ないスウェーデンでは、85%の人が経済成長の追求よりも環境保護を重視するのに対し、米国では同じ意見の人はわずか50%でした。一方、調査によると、製造業や運輸業などの分野の労働者は環境保護を優先する可能性が低いものの、労働組合への加入は彼らの環境保護への意欲を大幅に高め、労働組合への加入は経済的平等の向上と密接に関連していることが示されています。
維持に多大なエネルギーを必要とするヨット、自家用機、複数の車両、そして巨大な住宅を特徴とする超富裕層の消費パターンは、富裕層一人当たり年間数千トンのCO2を排出しており、新興の宇宙旅行は贅沢な排出量と地球へのダメージの新たなピークを迎えています。簡単に言えば、私たちは超富裕層を養う余裕がないのです。
しかし、彼らだけではありません。豊かな国々、そしてすべての国々の中でも比較的裕福な人々の過剰消費が、地球規模の問題の一因となっています。EUと英国では、人口の最も貧しい50%がパリ協定の一人当たり1.5℃目標まで排出量を削減する見込みである一方、最も裕福な10%は、その5~6倍の消費を続けると予測されています。つまり、過剰消費と消費主義は持続可能性に対する大きな脅威なのです。これは、地位不安(そして地位をめぐる競争)によって引き起こされ、さらに経済格差によって生み出される地位への不安がその根底にあります。国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて私たちがほとんど進歩していないこと、そして格差の大きい国々が著しく遅れをとっているのも不思議ではありません。
究極的には、私たちは地球を守り、すべての人々の幸福を保証しなければなりません。そのためには、不平等を劇的に削減し、気候変動に対して大胆な行動を起こし、経済目標を根本的に見直す必要があります。
これは、2009年の出版時に不平等に関する議論を巻き起こした書籍『スピリット・レベル』の分析を刷新するシリーズの最初の投稿である。詳細については、The Equality Trustが発行する『The Spirit Level at 15』リソースを参考まで。
ケイト・ピケットは、ヨーク大学健康科学部の疫学教授であり、同大学の正義と平等に関する研究の推進者である。また、RSA(王立協会)および英国公衆衛生学部のフェローでもある。ケイトの研究は、健康の社会的決定要因と健康格差に焦点を当てており、特に子どもの発達に興味を持っている。リチャード・ウィルキンソンと共著で、ベストセラー書籍『The Spirit Level』(2009年)と『The Inner Level』(2018年)を執筆している。ケイトはThe Equality Trustの共同設立者兼理事であり、Wellbeing Economy Allianceのグローバルアンバサダーでもある。
Original source: LSE
Image credit: David Syphers, Unsplash